お笑い芸人が言う「素人」は誰を指すのか /上岡龍太郎から松本人志以降
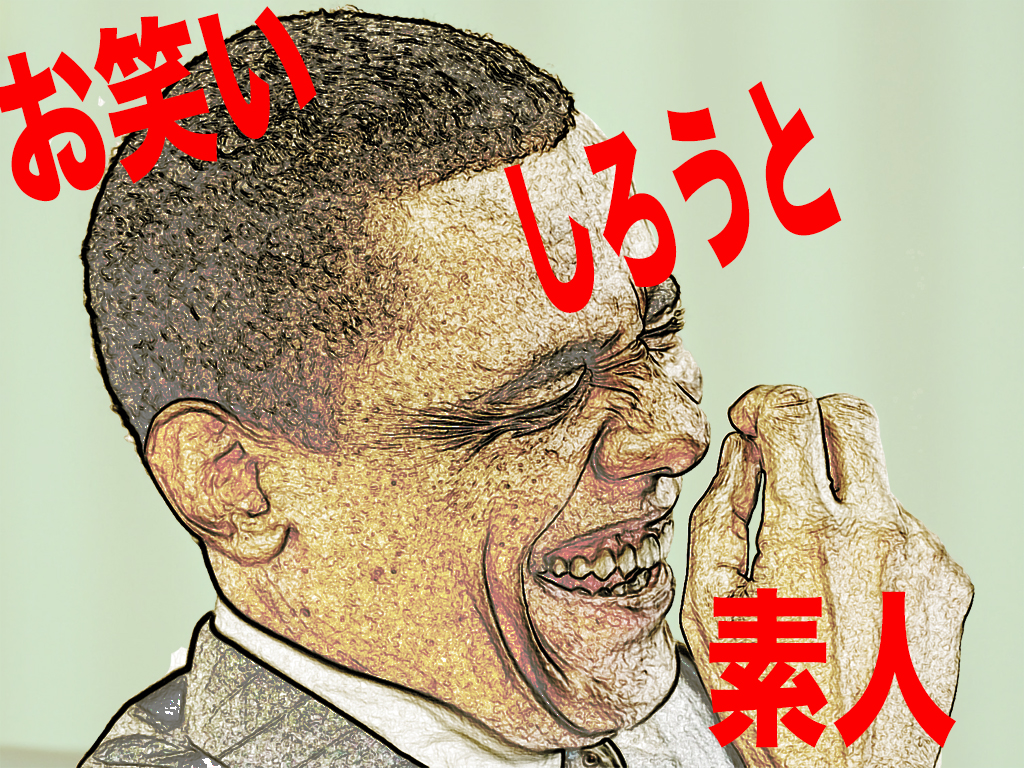
少し前に、知人が「お笑い芸人って、見ている人を素人って呼んで見下しているから嫌い」と言っているのを聞いて、何のことかと思いました。某お笑い芸人の暴言に始まり、それを批判したり擁護したりするお笑い芸人も一般客を「素人」と言っていたことから、「お笑いの玄人である我々に素人が口を出すな」という雰囲気を感じたそうです。なるほどと思いつつ「素人」という言葉の意味が変質していることを感じましたので、今回はお笑いの素人に関して書いてみたいと思います。
上岡龍太郎が言う「素人」
お笑い芸人がテレビで「素人」という言葉を連発するようになったのは、上岡龍太郎からだと思います。1987年から放送開始された「鶴瓶上岡のパペポTV」で全国的な人気を得た上岡龍太郎は、お笑いを芸として語る際に「素人」という言葉を用いて説明していました。これはお笑いが舞台芸からテレビ芸へと変わっていく中で、芸の質が変化したことを説明する際に使われていました。具体的には話し方の変化です。
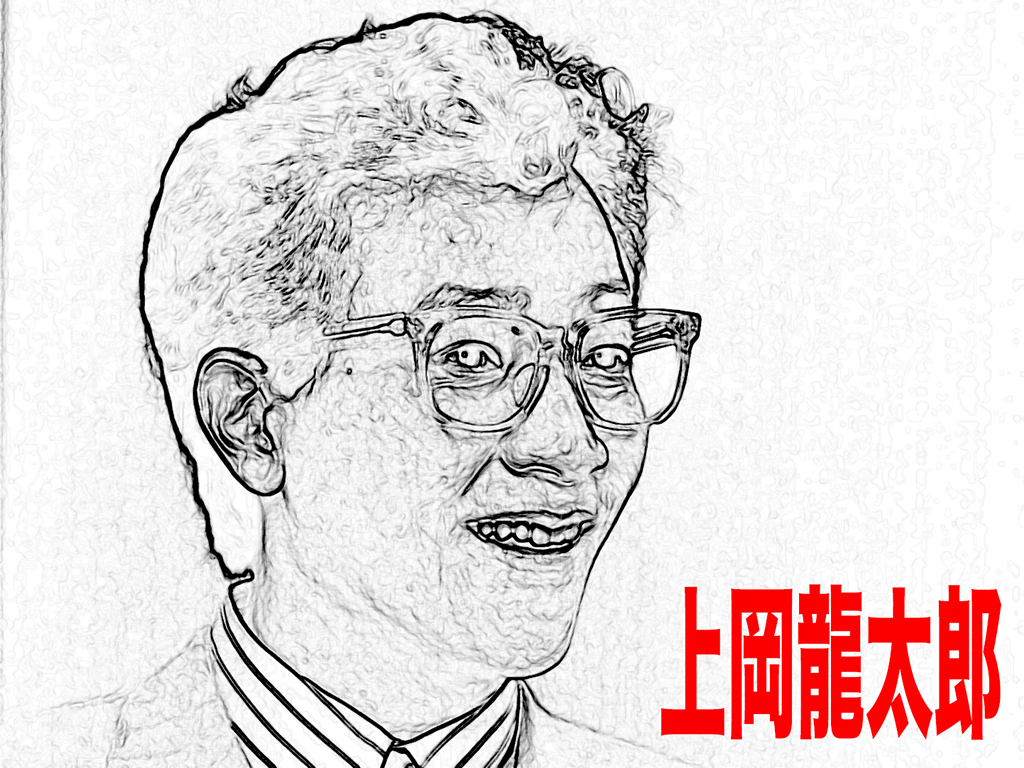
上岡によると舞台が中心だった頃のお笑い芸人は、突如としてやってきたテレビに戸惑ったそうです。舞台では客の反応や空気を読みつつ展開を考えていたのに対し、テレビは視聴者の顔が見えないので相手の反応がわからないまま続けなければならなかったからです。やがてテレビで大成功を収める人達も出てくると、上岡はテレビでウケるパターンに気が付きます。「有名人が見せるプライベート」「素人が見せる芸」の2つがテレビの鉄板コンテンツだと言っていました。「素人が見せる芸」というのは、具体的な名前を明かしませんでしたが、萩本欽一が視聴者からのお便りを元に番組を組み立てたことや、80年代前半に高視聴率だったオーディション番組「お笑いスター誕生」などの人気とも無縁ではなかったはずです。
上岡によると「素人が見せる芸」が人気になると、お笑い芸人が素人の真似をするようになったと言います。例えば上岡は番組の冒頭で番組内容を紹介する口上を立板に水がごとく話しますが、そのような玄人芸よりも一般の人の話し言葉の方が人気になったとしました。そのためお笑い芸人は玄人芸を捨てて、素人のように喋る素人芸が人気になり、その素人芸を極めたのが笑福亭鶴瓶であり明石家さんまだと言っていました。つまり上岡龍太郎が言及した「素人芸」とは、お笑い芸人らしくない素人のように普段使いの言葉で喋る芸のことでした。ですから、上岡の定義に当てはめると現在のお笑い芸人の大半は、素人芸をやっていることになります。
松本人志が言う「素人」
90年代に登場したダウンタウンの松本人志も、「素人」という言葉を使いました。ダウンタウンの功罪の一つに、お笑いが「わかる」という考え方を持ち込んだことです。お客の質に度々言及し、お笑いが「わかる」客であるかどうかがモチベーションに影響したことを当時から語っていました。1989年からフジテレビの「笑っていいとも」に出演を始めたダウンタウンは、観客に戸惑うことになります。すでに大人気だったダウンタウンの登場に客席は大きく盛り上がり、話している最中に何度も名前を呼ばれたりします。

渾身のボケをかましても、それを無視されて「松ちゃーん!」という観客の歓声にかき消されていく様子にうんざりし、客がお笑いをわかってないと嘆きます。どんなにネタを考えても、どんなに完璧なタイミングでボケても、お笑いがわかっていない客の前では笑いが起こることなく、ただキャーキャー言われて終わるだけでした。これに嫌気がさしたダウンタウンは、93年に「笑っていいとも」を降板することになります。松本はいくつかの意味で「素人」という言葉を使っていますが、特に言及していたのは「お笑いを理解しない客」または「お笑いの理解が浅い客」を素人と言っていました。
「ネタが面白くない」という声に対して「素人がごちゃごちゃ言うな」と返していたこともありますが、それは「お笑い芸人でない者が口を出すな」という意味ではなく「お笑いを理解していないのにネタに口を出すな」ということでした。必死で漫才をやっている最中にキャーキャーと奇声を上げて騒ぎ、漫才を全く聞いていないのに「あんまり面白くなかった」という声に対して、怒りをぶつけていたわけです。この松本の意見は理解できる面もありますが、反論が起こるべきものでした。お笑いというのは、その構造を理解していなくても笑えるものではないか?という反論が出るかと思いきや、そんな声はほとんどありませんでした。ダウンタウンは売れに売れてスーパースターになっており、その後はダウンタウンの無自覚な模倣が氾濫することになります。
現在のお笑い芸人が言う「素人」
2000年頃は、お笑い番組が次々と放送を開始します。「爆笑オンエアバトル」(NHK 1999年)、「はねるのトびら」(フジ2000年)、「Mー1グランプリ」(テレ朝2001年)、「R-1グランプリ」(フジ 2002年)、「エンタの神様」(日テレ2003年)、「笑いの金メダル」(テレ朝 2004年)、「爆笑レッドカーペット」(フジ 2007年)などが人気になり、大きな影響力を持っていきます。特に「Mー1グランプリ」は人気者への登竜門的な位置付けになり、出演者がしのぎを削る姿が話題になります。
グランプリは審査員のコメントも大きな話題になり、時には審査が偏っているという批判にも繋がりました。審査員の多くは大御所お笑い芸人であり、的を射るコメントが多かったのも事実で、お笑い芸人をお笑い芸人が批評するという流れが定着します。先ほどの松本人志が嫌っていた「お笑いを理解しない」人達の評価ではなく、まさに玄人がジャッジするわけです。そのため出演者も勝ち抜くために、一般客の反応よりも審査員の反応に神経を尖らせることになります。こうしたM-1世代のお笑い芸人は、視聴者からの批判を素人の意見と言うようになり、審査員席に座るお笑いの重鎮の意見と区別しました。この世代にとって「素人」は、お笑い芸人ではない人になったのです。
時代によって変わっていった「素人」
このように素人という言葉は、時代によって変化していきました。芸人らしさを捨てて一般人のように喋ることを「素人芸」と名付けた上岡龍太郎には、新しいお笑いの話芸という意味しかなく、観客を蔑むような意図はなかったと思います。しかしパペポTVで上岡と共演していた笑福亭鶴瓶も同じく素人という言葉を使うようになり、「笑っていいとも」で鶴瓶が「素人」という言葉を使うようになると、タモリも「芸能人ではない人」を指して「素人」と言っていた時期があります。この時点で、素人の意味が変わってきています。
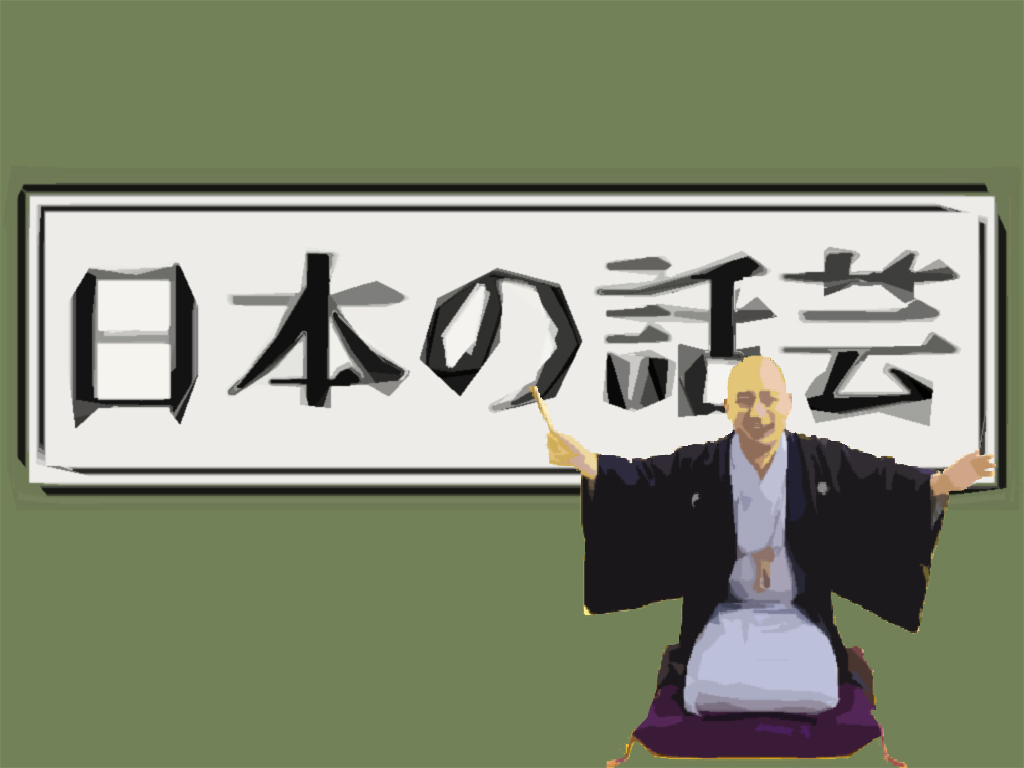
さらに松本人志が「お笑いの理解が浅い客」に対して「素人」と言い出し、さらにその後の世代は「お笑い芸人ではない人」を「素人」と呼ぶようになりました。これにより観客と芸人の断絶が起こっていて、お笑い番組が好きな人が多い反面、お笑い番組に関心を持たない人も増えました。最初に書いた知人のように「お笑い芸人って、見ている人を素人って呼んで見下しているから嫌い」という人も出てくるようになったわけです。
「素人」と「お前がやってみろ」
この流れの中で、お笑い芸人も変質してきたように思います。たびたび話題になる、面白くないと言われたお笑い芸人が「それなら、お前がやってみろ」という返しは、多くの批判が上がっています。プロが客に「お前がやってみろ」と言うのはプロ失格だという声が多いですが、その前提には芸人の打たれ弱さがあるように思いました。好きなことで食べていきたいけど、他人に批判されるのは耐えられないという打たれ弱さです。この打たれ弱さは素人発言にも繋がっているような気がしています。身内であるお笑い芸人とそれ以外を区別し、身内以外からの批判をシャットアウトして自分を守りたいのではないでしょうか。これは本件とは少し趣旨が違うので、また別に考えてみたいと思います。
まとめ
お笑い芸人が言う「素人」に関して書いてみました。上岡龍太郎、松本人志、そして現在の若手芸人の言う「素人」は、それぞれ意味が違うと思います。そしてお笑い芸人以外を「素人」と言うようになった現在、ファンとお笑い芸人の間には断層ができてしまったように感じています。面白くないと言われたお笑い芸人が「お前がやってみろ」と言って批判されましたが、飽和状態のお笑い芸人の感覚がズレてきているような気がしてなりません。テレビ離れと共にお笑いが飽きられたという声もチラホラ聞こえてきましたが、こういったことが一因なのかもしれないと思いました。
