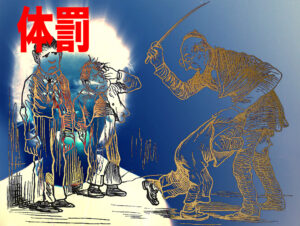ゆとり世代の実態は「ゆとりがない」世代だったのではないだろうか

思い返せば2008年ぐらいには、ビジネス誌に「ゆとり世代が新入社員としてやってくる」という記事が特集されだし、まるで会話ができない異星人がやって来るかのような危機感を煽る記事が出ていました。彼らは一様に学習力が低く、これまでとは全く異なる思考をするような内容が多く、取り扱いに困る企業が増えるから今から準備しておけ的な内容でした。こうしてゆとり世代は誤解されていきました。今回はゆとり世代とは何だったのかを考えていきます。
Contents
ゆとり世代とは
ゆとり世代とは文部科学省の学習指導要項の改訂により、生まれた世代とされています。詰め込み教育の反省から1970年に日教組が「ゆとりある学校」を提起し、そこからさまざまな議論が行われていきました。偏差値偏重主義とも言われた受験戦争の時代を経て、1998年に「完全学校週5日制」(いわゆる週休2日)などを盛り込んだ学習指導要項が成立します。
試験が終わるとすぐに忘れてしまう詰め込み教育を削減し、「調べ学習」など思考力を身につける学習が多く盛り込まれ、「生きる力」の育成を目指すものとされたのが特徴です。小中学校では学習内容のうち3割を削減され、「ゆとりある学校」を目指していました。学校が早く終わることで、その時間を画一的な学校の勉強だけではなく、他のものにも目を向けてもらいたいという考えもありました。
ゆとり世代とは、このゆとり教育を受けた世代を指します。ただし学習指導要項は何度も改定されているので、ゆとり世代の定義は複数あります。しかしここでは1998年に成立し2002年から実施された学習指導要項の下に義務教育期間を過ごした世代とし、2011年に改定されるまでの世代をゆとり世代と呼ぶことにします。そのため1987年4月2日生まれから2004年4月1日生まれを指すことにします。
叫ばれた学力低下
①PISA2003の衝撃
PISAとはOECD(経済協力開発機構)加盟国を中心に実施される国際的な学習到達度調査で、現在は世界79の国と地域、生徒約54万人が参加しています。対象は15歳の学生で、3年ごとに実施されます。日本は2000年から導入しました。そして2003年に実施されたPISAの結果に、衝撃が走ることになります。2000年の調査に比べて、2003年の結果で大きくランクダウンしたからです。
数学的応用力1位→6位
科学的応用力2位→2位
読解力8位→14位
2002年からゆとり教育が実施されていたため、ゆとり教育が学力低下を招いているとメディアが大騒ぎしました。しかし2000年と2003年では参加国数が違いました。2000年は32カ国が参加したのに対し、2003年は41の国と地域が参加しています。参加国数が違うのに、順位を比較するのは正確ではありません。順位が下がったとしても、単に分母が大きくなったからかもしれないからです。

さらにゆとり教育が実施されてから1年しか経っていないのですから、ゆとり教育以前の教育に問題があった可能性もあります。PISAの対象は15歳なので、中学校3年生です。PISA2003を受けた生徒は、小学校1年生から中学校2年生までは以前の授業を受けており、中学校3年生になってからゆとり教育のカリキュラムで授業を受けただけなのです。
PISA2003の結果により、ゆとり教育が学力低下を招いていると言われていましたが、恣意的な報道のよって作られた感がします。一方、PISA2012では最初からゆとり教育を受けていた世代が数学的リテラシー7位、科学的リテラシー4位、読解力4位と順位も向上しましたが点数でも過去最高の大健闘をしました。この時は65の国と地域が参加していますから、ゆとり教育により学力が大幅に向上したといえるかもしれません。
そして2011年にゆとり教育が終わると、徐々に順序を下げていきPISA2018では数学的リテラシー6位、科学的リテラシー5位、読解力15位となりました。点数も大きく下がっており、読解力の低下が著しく、脱ゆとり教育が失敗しているのではという声が出たほどです。ゆとり教育が学力低下を招いたというのは、あまりに短絡的な考えだと思います。
②円周率3.0の嘘
2002年の小学校学習指導要綱の改訂で、円周率を3.0と教えることになったという間違った風説が流布されました。これは学習指導要綱に「目的に応じて3を用いて処理」と書かれたことが、誤解を招いた結果でした。しかし学習塾大手の日能研が大々的なキャンペーンを張り、広告を大規模に展開したためメディアにも取り上げられることになりました。以前から小数点の計算を縮小することなどが問題視されていたゆとり教育において、この「円周率3.0」はゆとり教育のダメな点の象徴として語られることになりました。
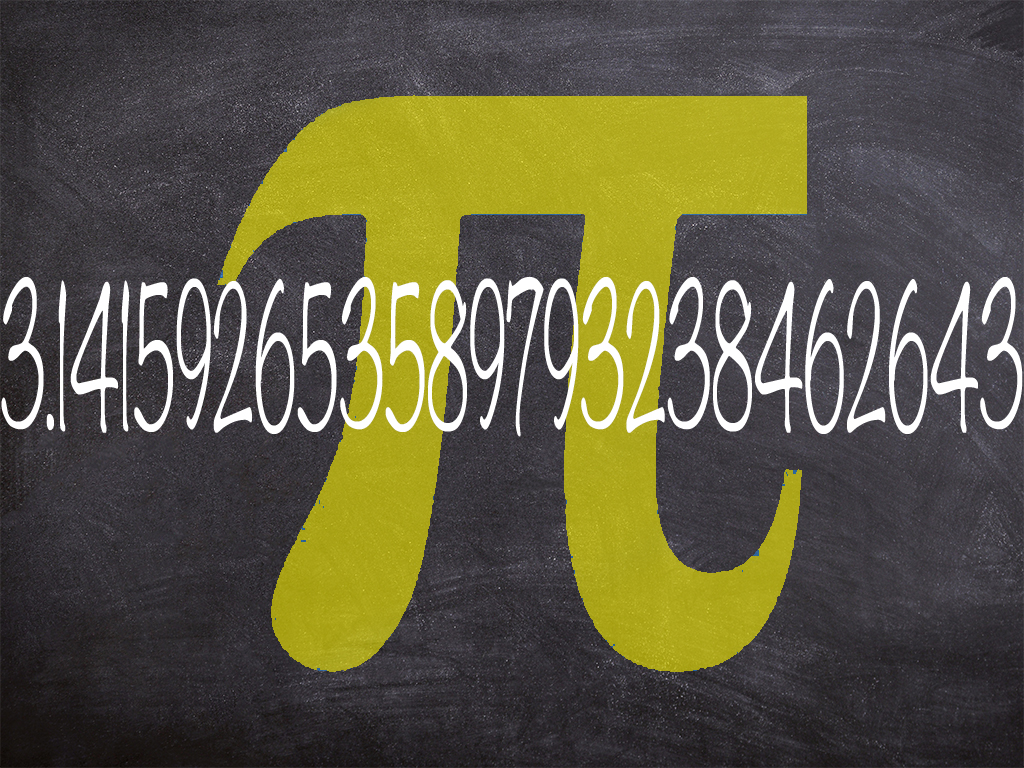
学習塾の大規模広告展開
1990年代末に学習指導要領の改訂内容が明らかになると、学習塾はゆとり教育の危機感を煽る広告を打ち出しました。子供の将来を危惧するCMやテレビ番組が増えた結果、学習塾の市場が拡大しています。2002年の日本経済新聞には、主要な塾の生徒が軒並み10〜20%増加したと報じられました。また大手塾のキャンペーンにより、個人経営の塾や中小規模の塾が衰退して大手に生徒が集中するようになります。
ゆとり教育により小中学校の授業が減り週休2日が実現しましたが、政府の思惑だった自主的な学習の時間を増やすことではなく、生徒は学習塾で時間を費やすことになりました。塾に通い出す年齢はどんどん低年齢化していき、中学受験をするなら最低でも小学校4年生から塾に通わないと間に合わないと言われるまでになっていきます。ゆとり世代の中には「ゆとりがない世代」として学生時代を過ごした人達が、少なからずいたわけです。
2度目の就職氷河期に突入
1987年生まれの初期のゆとり世代が就職活動を行ったのは、22年後の2009年です。この年は前年のリーマンショックにより、2度目の就職氷河期が始まっていました。1999年に0.48だった有効求人倍率は、2006年、2007年には1.0を超えて1993年頃から始まった就職氷河期が終焉したかに思われていました。しかし2008年のリーマンショックで有効求人倍率は2009年に0.47になってしまいました。バブル崩壊後を上回る最低の有効求人倍率です。就職が極端に難しく、ゆとりなど皆無な就職活動を強いられました。そしてやっと入社したら「ゆとりだから」とバカにされることになってしまいました。
「ゆとりだから」という侮蔑
2008年頃からビジネス誌にはゆとり世代が入社してくると危機感を煽り、ゆとり新入社員の対策などを特集していました。彼らは入社前から偏見の目で見られていたため、何かある度に「これだから『ゆとり』は」と言われることになります。学力が低下しているという根拠はあやふやで、現在の研究では学力が向上したというデータと低下したというデータがあり、ゆとり教育が成績にどのような効果を与えたのかは議論が残ります。しかし偏見により、ゆとり世代は使えないとか理解不能なことを言うなどのレッテル貼りが横行しました。今もその名残はあります。

そして文部科学省は2011年に脱ゆとりを宣言したのですが、ゆとり教育を受けた世代から「私たちは失敗作なのか?」という声が上がりました。メディアや学習塾の宣伝によってレッテル貼りされたゆとり世代は、やっと入社した会社からもレッテル貼りをされて苦しんでいたところに、文部科学省からも否定されたように感じたようです。彼らにゆとりがあったように全く見えないのは、気のせいでしょうか。
94年組と呼ばれるゴールデンエイジ
スポーツの世界では、94年組と呼ばれるゴールデンエイジが度々話題になります。ゆとり教育が行われた2002年から2011年の間に義務教育を受けた世代で、94年生まれは小学校2年生からゆとり教育のカリキュラムで育っています。94年生まれのアスリートには野球の大谷翔平、フィギュアスケートの羽生結弦と村上佳菜子、水泳の萩野公介と瀬戸大地、バドミントンの桃田賢斗、スピードスケートの高木美帆、レスリングの土性沙羅と川井梨紗子、バスケットの渡邊雄太などがいます。

94年組が豊作になった理由について、多くの人がゆとり教育により学校のカリキュラムが減ったことを挙げています。週休2日になり、帰宅時間が早くなったことでスポーツに打ち込む時間が増えたという訳です。これだけを理由に求めるのは無理があると思いますが、練習時間が増えたことは間違いないと思います。またこの世代ぐらいからSNSが浸透し、ピア効果が全国レベルで発生したという指摘もあります。ピア効果は同じような目的を持った人達が、同じ環境に集まると互いを見て切磋琢磨するようになることです。
94年組の前後にもボクシングの井上尚弥(93年生まれ)、ゴルフの松山英樹(92年生まれ)、バスケットの馬瓜エブリン(95年生まれ)などがいます。これらの選手が、ゆとり教育によって生まれたかはわかりません。さまざまな要素が絡んでのことだと思いますが、ゆとり教育が失敗だったと断じるわけにはいかない理由にはなると思います。
まとめ
ゆとり教育が失敗だったとされるのは、かなり偏った見方でしかないと思います。ゆとり教育が与えた影響についてはさまざまなレポートが出されていて、ゆとり教育によって学力が向上したデータも低下したデータもあります。学習塾で多くの時間を過ごし、就職氷河期に直面し、会社に入ると「これだからゆとりは」と言われてしまいました。ゆとり教育を受けた世代は「ゆとり世代」と呼ばれますが、「ゆとりがない世代」だったように思います。