可処分時間の奪い合い /井上尚弥の人気が高騰する理由
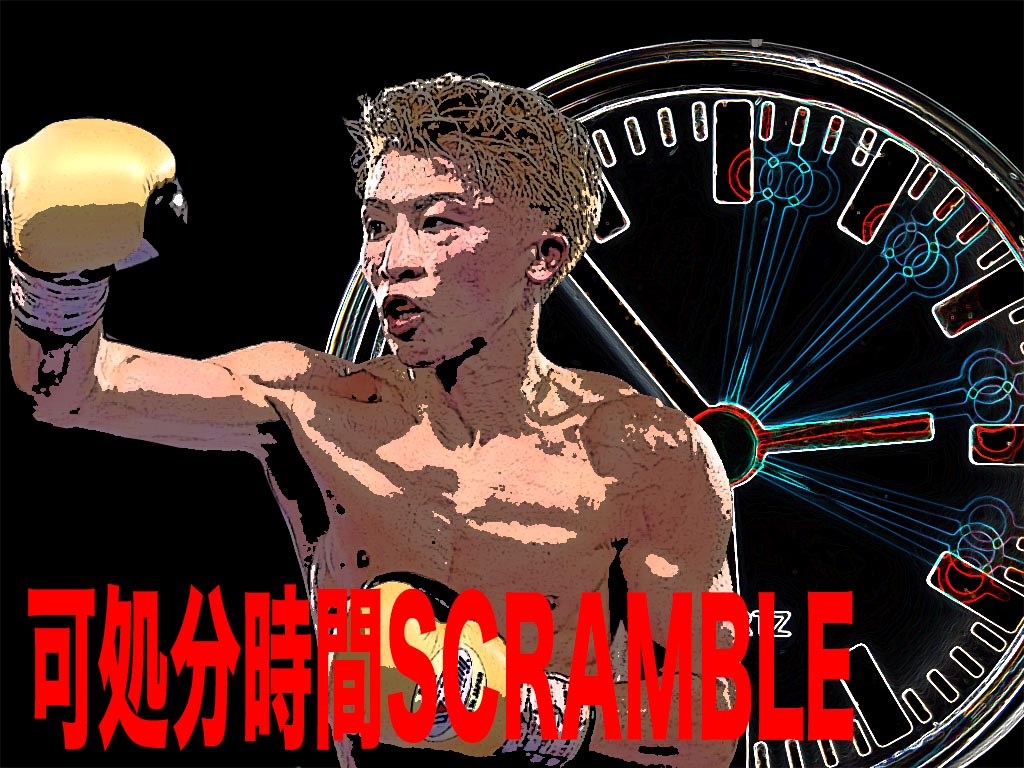
ヨーロッパサッカーの強豪、スペインのレアル・マドリードの会長であるフロンレンティーノ・ペレスは2021年4月に「若者はもはやサッカーに興味がない。彼らの気を引く他のプラットフォームが多くある」とサッカー人気の危機を訴えました。「より魅力的な試合を行うために、解決策を見つける必要がある」として、その1つとして現行の90分の試合時間を短縮する案を掲げました。多くのサッカー関係者に猛反発を受けたペレス会長ですが、可処分時間の奪い合いになっている現代において、適切な問題提起だったように思いました。
Contents
可処分時間とは
可処分時間とは近年になってマーケティングで使われるようになった言葉で、人が自由に使える時間のことです。1日24時間の中で食事や睡眠などの必要な時間、さらに家事や仕事などの時間を引いて残った時間を可処分時間と呼んでいます。もともと可処分所得(収入から税金や社会保険料を差し引いた自由に使えるお金)という言葉があり、お金を時間に置き換えたのが可処分時間という考え方になります。
以前は可処分時間の使い方はテレビや読書、音楽鑑賞などの趣味に使われていました。しかしスマホが普及してからは、可処分時間の多くをインターネットに使う人が増えていきました。現在はNetflixやAmazonプライム、YouTube、各種SNSサービスやスマホゲームなどがこの可処分時間の奪い合いで激しい攻防を演じていますが、当然ながらテレビも出版社もここに食い込みたいと思っています。また飲み屋やカラオケ店なども同様で、自由に使える時間をどこで使ってお金をいくら落とすかが重要な関心になっているのです。
ペレス会長の「彼らの気を引く他のプラットフォームが多くある」という発言は、ネットの普及によって動画などを見る人が増えたためサッカー中継を見る人が減っていることに危機感を持ったからだったと思われます。

人気低迷を懸念する欧州サッカー
高騰した放映権料
実は欧州サッカーは未曾有の好景気にあります。特にイギリスのプレミアリーグは顕著で、ここ20年でクラブ収入が大幅に上昇しています。その収入の大部分はテレビの放映権料で、サブスクで独占放送することで高い収益を上げることが可能になっていました。その放映権料は20年間で3倍以上になっており、プレミアリーグ全体で60億ユーロを突破しました。この放映権料から得られる利益の半分は全てのクラブチームに平等に分配され、残りの25%はリーグの順位によって、残り25%はテレビ放送の試合数によって分配されています。

プレミアリーグではこうして多額の資金がクラブチームに流れ、そのため選手の移籍金が毎年のように2倍になるバブル状態になっています。これがいつまでも続くとは考えられず、実際に放映権料の値下げ交渉なども始まっていて一部の関係者は強い危機感を持っています。この放映権料はファンの財布から出たお金です。一部では放映権料が高騰しすぎてサッカー単独で見ると赤字になっているサブスク会社もあり、サッカービジネスは曲がり角に来ているとの指摘も出ています。
試合時間の長さは問題か
YouTubeで最も再生が多い動画の多くは、10分から15分と言われています。しかしサッカーは試合時間が90分で、ハーフタイムや何やらを含めると2時間ぐらいをテレビの前に縛られることになります。限られた可処分時間の中で2時間をサッカーに費やすことができるかということになります。コアなサッカーファンは2時間なんて惜しくもないでしょうが、ライトなサッカーファンや初めて見る人には敷居が高いと思われても仕方ありません。
最近は日本のアニメが海外でも人気になっていますが、日本の30分枠のアニメはAmazonプライムやNetflixではCMがないため、20分程度で見終わることができます。この時間の短さが人気の理由の1つと指摘する声もあり、サッカーの2時間はかなり長尺のコンテンツと言えるでしょう。そしてサッカーはどちらが勝つかわからず、必ずしも望んだ結末を見ることができるとは限らないのです。
高度なシステムで運用される現代サッカー
また現代サッカーではシステムが高度化しすぎており、特にジョゼップ・グアルディオラがプレミアリーグのマンチェスター・シティで指揮をとるようになった2016年からそれが顕著になりました。その結果、かつてのファンタジスタと呼ばれるスター選手に頼る戦い方では勝てなくなり、強固なシステムを確実に実行する堅実な選手が重宝されるようになっています。
サッカー日本代表に例えるなら、かつての中田英寿のスルーパスや中村俊輔のフリーキックは初めてサッカーを見る人にも凄さが伝わりますが、オフ・ザ・ボール(ボールを持っていない時間)でのポジショニングの上手さが監督に評価される現状は、サッカーを見慣れた人でないとわかりにくいでしょう。初めてサッカーを見るひと、あまりサッカーに詳しくない人にはわかりにくいサッカーが展開されているわけです。
メジャーリーグ人気の低迷
メジャーリーグも人気の低迷が言われています。観客動員数が2012年ぐらいから低迷していて、米紙ニューヨークタイムズによると、2007年のレギュラーシーズンの観客動員数は8000万人近かったのに、2019年シーズンは6850万人に減っているそうです。その原因としてはヒューストン・アストロズのサイン盗みなどの不祥事、野球のデータ分析が進んだことにより、三振かホームランかの大味な傾向が強くなったことなどが挙げられています。

またチケットやテレビ視聴料の値上げ、試合時間の長さなども要因としてあがっています。1980年代の試合時間は平均して2時間30分程度でしたが、今や3時間を超えています。試合のテンポが遅いため若い世代が離れているとも言われ、現在のメジャーリーグを支えているのは50歳代以上のファンが中心だそうです。
井上尚弥の試合はYouTube動画1本分
井上尚弥の過去10試合を振り返ってみましょう。2017年9月のアントニオ・ニエベス戦から2022年6月27日のノニト・ドネア戦までです。12ラウンドまで戦って判定決着になったのはWBSS決勝のノニト・ドネア戦のみで、それ以外の9試合はKOまたはTKOで決着しています。では何ラウンドで試合が終わったかというと、6R 3R 1R 1R 2R 7R 3R 8R 2Rです。実に6試合が3R以内に終わっているのです。ラウンド間のインターバルが1分ありますが、それを含めても井上尚弥の試合の半数以上は10分以内に終了しているわけです。

YouTubeの動画は10分から15分程度にまとめたものが人気が高いとされていて、そのため15分以内のものが多くあります。井上尚弥の試合の多くはYouTube動画1本分程度の長さしかなく、現代の動画コンテンツとして最適な時間になっていることがわかります。それに加えて井上尚弥の試合は強打でのKOが多いため、初めてボクシングを見る人にもわかりやすい強さと凄さを伝えています。コンテンツの時間と面白さが現代のニーズに合っているため、高い人気を誇っているのも当然だと言えるでしょう。
今後のスポーツは時間短縮が必要なのか
スポーツの試合時間は、今後も議論されるように思います。アメリカではプロバスケットリーグのNBAが人気ですが、試合時間は2時間から2時間30分ぐらいです。アメリカンフットボールのNFLは3時間ぐらいで、メジャーリーグは3時間を超えています。スポーツの中で野球は試合時間がかなり長い方になります。そしてサッカーはそれらより短いですが、ペレス会長のように試合時間が長いという意見も出ていて、試合のスムーズな進行や試合時間そのもののが議論されると思います。
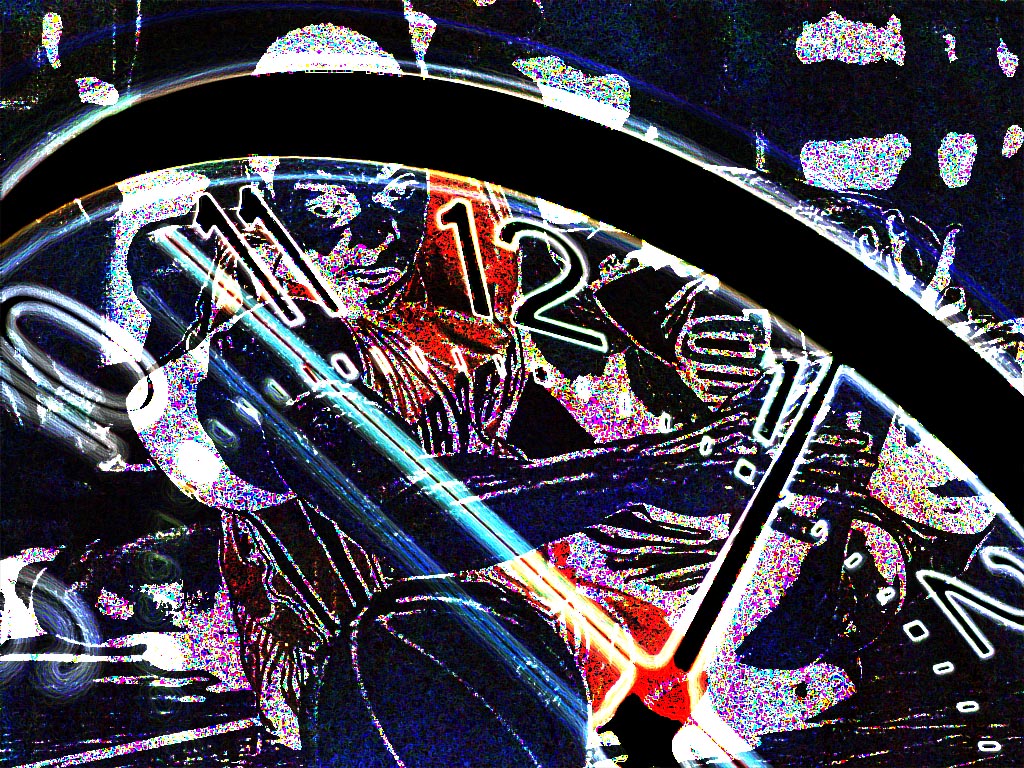
しかし試合時間は競技そのもののゲーム性を左右する問題なので、安易に短くすることはできないはずです。またサッカーやバスケットボールのように試合時間が決まっている競技と、野球やバレーボールのように試合時間が決まっていない競技では、試合時間の考え方が異なると思います。しかし可処分時間の奪い合いが起こっている中、長時間であっても人を惹きつけるようなコンテンツとして育てられるか否かは大きな問題になると思います。
まとめ
現在はスポーツに限らず、可処分時間の奪い合いが起こっています。その中で試合時間が問題になることがあり、今後も試合時間に関する議論が起こるでしょう。その一方で、ボクシングの井上尚弥は10分以内に試合を終わらせることが多く、狙っている訳ではないでしょうが時代のニーズにマッチしています。さらにKOというわかりやすい結末で終わるので、井上尚弥が人気になるのも当然だと思います。日本でもサッカー日本代表人気が低迷し、プロ野球人気も徐々に低下していると言われています。スポーツビジネスが曲がり角に来ていると思います。

